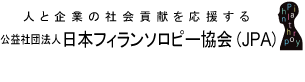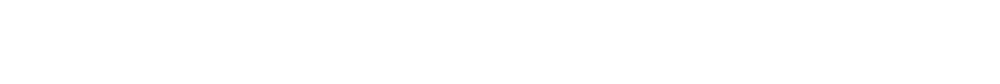
2025年4月号
Date of Issue:2025.4.1
2025年4月号
Date of Issue:2025.4.1
◆ 巻頭対談/2025年4月号
「ビジネスと人権」研究会を振り返って
「ビジネスと人権」研究会座長/公益社団法人日本フィランソロピー協会理事
河野 通和 さん
公益社団法人日本フィランソロピー協会理事長
髙橋 陽子 さん
髙橋 当協会として「ビジネスと人権」に取り組むきっかけになったのは、河野さんから、真正面から人権について考えてみてはどうかという言葉をいただいたことです。企業の社会貢献の企画・運営に携わる中で、私たちの活動が社会課題解決や新しい価値創造につながっていくのかという不安やもどかしさを感じていたこともあって、まずは機関誌で「ビジネスと人権」(2024年4月号)を特集しました。そこで改めて、人権問題をビジネスの中でどう捉えるかではなくて、そもそも人権とは何か、人権を守るとはどういうことなのかという発想の転換、頭の中でパラダイムシフトが必要だと感じました。そこで河野さんのお力をお借りして、研究会を開催することにしました。

河野 機関誌の巻頭インタビューで 土井香苗さん(ヒューマン・ライツ・ウォッチ日本代表)は、「日本は人権に関する体制づくりがなかなか前進しない。でも企業が現場で取り組んでいるその動きは決して小さくなくて、企業のポテンシャル、影響力は大きい」と話されました。ビジネスと人権について、企業が動けば大きな力になり、やがて社会を変えていくのではないかと感じたし、協会の活動とも符合すると思いました。土井さんの発言は後押しになりましたね。1990年代以降のグローバル化の流れの中で、人権を侵害する事態が広がりました。企業はリスクヘッジとして課題を抽出し、ルールや方針を決めたり、SDGsなどの関連部署を設置するなど、さまざまに対応しています。でもそれがルーティーン化すると「魂」の部分が希薄になりがちです。
人権意識は時代の変化とともに移り変わるものです。だからこそ、そもそも人権とは何かということを考えることで、新しい気づきや発想が生まれるのではないか。その意識の覚醒が必要ではないかと思いました。
2023年にジャニーズの問題が発覚し、2025年はフジテレビの問題がありました。企業において人権問題を扱う部署の担当者が、もう一度自分の気持ちを耕し直して社内に発信する、あるいは経営層に対して強く進言するタイミングなのではないか。そういう意味で、今回の研究会開催は良い機会だったと思います。
人権意識は時代の変化とともに移り変わるものです。だからこそ、そもそも人権とは何かということを考えることで、新しい気づきや発想が生まれるのではないか。その意識の覚醒が必要ではないかと思いました。
2023年にジャニーズの問題が発覚し、2025年はフジテレビの問題がありました。企業において人権問題を扱う部署の担当者が、もう一度自分の気持ちを耕し直して社内に発信する、あるいは経営層に対して強く進言するタイミングなのではないか。そういう意味で、今回の研究会開催は良い機会だったと思います。
髙橋 習慣化するまでには至っていないから、あえて問い直すことが必要ですね。今回参加してくださった皆さんは、企業人、職業人としてはもちろんですが、それ以前に人間として非常に真摯に、真剣に向き合ってくださった。そのことに感謝しています。
河野 参加者の肉声を聞くことができたし、皆さんからいろいろと教わることもありました。協会の活動の積み重ねがあって、その思いが結集したような気持になり、うれしかったですね。
髙橋 参加者の皆さんが、それぞれの会社に持ち帰られてどうフィードバックされているか、知りたいですね。現状や成果を出し合って、それを共通の財産にしていく作業もできたらいいなと思っています。
河野 企業の内なる意識変化をどう広げられたのか、期待も込めて聞いてみたいですね。協会としてもきちんと火をくべていかなければなりませんね。
講師の方々も、一人の人間として、「あわい」の中から発する言葉でお話してくださいました。村木厚子さんはご自身が体験した切実なこと、その過程で考えたこと、その後実践されていることを、力強い言葉で、わかりやすく語ってくださいました。
鈴木江理子さんは、学者としての知見だけではなく、実践者として感じていることにもつなげてくださった。堂目卓生さんは、人権を考える大前提は共感だとおっしゃった。日本社会の中で可視化されていないこと、構造化され過ぎて常識だと思い込んでいることはたくさんある。
私たちも企業人として生きている時間と個人として生きている時間を明確に切り分けているわけではありませんから、メディアが伝えきれていない部分も含めて、今回人権についてさまざまな角度から掘り起こせたことは良かったと思います。それぞれが語られた言葉は、プラクティカルですぐに役立つわけではないかもしれませんが、人権感覚の根本のところを考えるためには、どのテーマも必要だったと思います。
講師の方々も、一人の人間として、「あわい」の中から発する言葉でお話してくださいました。村木厚子さんはご自身が体験した切実なこと、その過程で考えたこと、その後実践されていることを、力強い言葉で、わかりやすく語ってくださいました。
鈴木江理子さんは、学者としての知見だけではなく、実践者として感じていることにもつなげてくださった。堂目卓生さんは、人権を考える大前提は共感だとおっしゃった。日本社会の中で可視化されていないこと、構造化され過ぎて常識だと思い込んでいることはたくさんある。
私たちも企業人として生きている時間と個人として生きている時間を明確に切り分けているわけではありませんから、メディアが伝えきれていない部分も含めて、今回人権についてさまざまな角度から掘り起こせたことは良かったと思います。それぞれが語られた言葉は、プラクティカルですぐに役立つわけではないかもしれませんが、人権感覚の根本のところを考えるためには、どのテーマも必要だったと思います。
髙橋 講師の方には事前にこちらの意図をお伝えしましたが、根幹は共通していたように思います。聞き手との間に生まれた場の力も大きかったのではないでしょうか。
河野 自分の言葉が響いているなと感じられたところはあったと思います。聞き手も、企業を代表して参加しているわけですが、それぞれが自らの文脈に引き込んで、これはうちの会社で使える、使えないということではなく、一人の人間としてちゃんと耳を傾けてくださった。座長としてもこれは非常にうれしかったですね。
企業において、人権を担当する部署はどのような位置づけなのでしょうか。長期的な視野に立った時に、企業の評価として大事な指標を担うわけですが、戦略的に重要な部署だと思われているのか。それとも建前、お飾り的な位置づけになっているのか、あるいは孤立感を持っているのか。
企業において、人権を担当する部署はどのような位置づけなのでしょうか。長期的な視野に立った時に、企業の評価として大事な指標を担うわけですが、戦略的に重要な部署だと思われているのか。それとも建前、お飾り的な位置づけになっているのか、あるいは孤立感を持っているのか。
髙橋 小島慶子さんは、女性の役員は増えているものの、まだまだ中核の部署には配置されないことを「ドーナツ型女性起用」と表現されていました。同じようにサステナビリティや人権に関する部署も、企業全体から見れば、まだマイノリティだと思います。だからこそ、今回の研究会は第一歩として意味あるものだと思いますし、意味を持たせるようにしなくてはなりません。
フィランソロピーの真髄は人間の共感力です。平和への希求も人権を守ることも、フィランソロピーという哲学をベースに、ビジネスの世界で体現できるものにしていかなくてはならないと思っています。
フィランソロピーの真髄は人間の共感力です。平和への希求も人権を守ることも、フィランソロピーという哲学をベースに、ビジネスの世界で体現できるものにしていかなくてはならないと思っています。
河野 やはり「共感革命」ですね。共感をどのように企業の中にインストールしていくのか、道徳律としてプッシュしていくのか。そこは大事なポイントだと思います。
髙橋 村木さんの回で話題に上った「性弱説」も、ビジネスと人権を考える上で大切ですね。企業もビジネスマンも、強者であらねばならないという思い込みがありますが、皆それぞれに弱さや辛さがある。そこには共通する部分もありますから、人権の問題も共感によって自分事として考えられるはずです。そうなると競争力がなくなると言われるかもしれませんが、自分に合った仕事や職場で、少しずつでも戦力になればいい。
河野 性弱説はいろいろな意味を含んでいますね。命の成り立ちそのものが弱さとつながっているわけで、それを考えさせられた大きな出来事はやはり新型コロナウィルスだったのではないか。
稲葉俊郎さんのお話が興味深かったですが、パンデミックになって、文明の根幹を揺るがすような状況に陥った。地球温暖化、気候変動もそうですが、人類がいかに脆弱な基盤の上に乗っているのかがわかったし、このまま行くと底が抜けるという危機感が広がりました。命そのものが本当にきわどいところに乗っている。コロナが人類の弱さを可視化してくれたと思うのですが、もはや喉元過ぎればになっています。このまま分断や格差、環境の劣化などが進めば、またコロナ禍のようなことが起きるでしょう。今の文明が思っているほど盤石ではないという意味での性弱説について、私たち全員が考えなければなりません。
稲葉俊郎さんのお話が興味深かったですが、パンデミックになって、文明の根幹を揺るがすような状況に陥った。地球温暖化、気候変動もそうですが、人類がいかに脆弱な基盤の上に乗っているのかがわかったし、このまま行くと底が抜けるという危機感が広がりました。命そのものが本当にきわどいところに乗っている。コロナが人類の弱さを可視化してくれたと思うのですが、もはや喉元過ぎればになっています。このまま分断や格差、環境の劣化などが進めば、またコロナ禍のようなことが起きるでしょう。今の文明が思っているほど盤石ではないという意味での性弱説について、私たち全員が考えなければなりません。
髙橋 まずは一個人として、身近な暮らしや仕事において人権を考え、その延長線上で職業人・企業人としてどうあるべきかを考えてみる。人権はシームレスに存在しますから、企業の影響力の大きさを考えると、人権を守ることにおける企業の果たせる可能性は大きいと思います。もっとも、国のリーダーがまず人権を真ん中に据えて国づくりを考えてほしいですが。
河野 フランスの人類学者、エマニュエル・トッドが『西洋の敗北 日本と世界に何が起きるのか』で書いていますが、トランプ政権は米国の未来を明るく良きものにしていくのではなく、世界の混迷を深めるでしょう。現実社会をどうしていくか、世界の中で日本はどう生きるべきか。打たれないように首を縮めなければならないときもあるでしょう。日本は小さな国ですが、その中で国際社会においてどう立ち居振る舞うのか、英知を結集しなければなりませんね。
髙橋 SDGsの観点から言えば、社会課題への取り組みもこれまではフォアキャスティングの捉え方でしたが、それでは自然環境・社会環境の劣化を止めるには程遠い。2050年のあるべき姿を描き、バックキャスティングしてSDGSの目標を達成しようという流れです。
人権問題はあらゆるゴールを達成するためのベースにあるものだと思います。だとすれば、人権の本質をしっかり見据えて取り組まないと解も見えてきません。今回の研究会では、講師や参加者の皆さんから「そもそも人権とは?」「人権を守るとは?」などの本質的な問いかけが投げかけられ、真摯な議論がなされました。これを周囲の人たちと共有し、共感の輪を広げていかなければなりませんね。
人権問題はあらゆるゴールを達成するためのベースにあるものだと思います。だとすれば、人権の本質をしっかり見据えて取り組まないと解も見えてきません。今回の研究会では、講師や参加者の皆さんから「そもそも人権とは?」「人権を守るとは?」などの本質的な問いかけが投げかけられ、真摯な議論がなされました。これを周囲の人たちと共有し、共感の輪を広げていかなければなりませんね。
河野 声を上げることもひとつのアクションです。どれだけの人を動かせるかとなると数は限られるかもしれませんが、参加者には確実に届いたはずですし、そこからまた広がっていくでしょう。
髙橋 「百年河清を俟つ」(ひゃくねん かせいを まつ)などと諦観するのではなく、覚悟をもって高みを目指し、声を上げ続け、歩みを進めていきたいものです。
(2025年2月27日 公益社団法人日本フィランソロピー協会にて)
機関誌『フィランソロピー』巻頭対談/2025年4月号 おわり